新たなキャリアを考えるうえでスーパーマーケット業界への転職は、選択肢の一つとしておすすめできます。
とはいえスーパーの従業員の仕事ぶりといえば「商品を棚に並べる」「レジで商品と代金の受け渡しをする」くらいしか思い浮かばないかもしれません。
実は、スーパーマーケットとは人々の食生活の基盤を支える重要なインフラであり、そこで働いている人々の社会への貢献度はめちゃくちゃ高いのです。
また未経験者でも比較的就職しやすく、キャリアアップもしやすい面があります。そのため、フリーターが長かったり、引きこもり生活を続けていたりと、キャリアになんらかのコンプレックスを抱える方におすすめできる業界です。
この記事では、スーパー業界へ就職を検討している人向けに、スーパーマーケットで働くメリット・デメリットや、向いている人の特徴について解説します。
この記事を読むとあなたのココが変わります!
- スーパーで働く魅力がしっかりつかめる
- スーパーで働いてみたくなる
執筆者(だいすけ)のプロフィール
某ドラッグストアに3年勤務し店長経験
某スーパーマーケットチェーンに契約社員として転職。その後1年半で正社員へ登用
入社3年目で部門マネージャー、5年目でスーパーバイザーを経験
8年目には店長へ昇進。年収600万円達成!
現在は脱サラし、フリーランスのWebライターとして活動中。
厳しいとされる小売業界でわりとトントン拍子に昇進をはたし、業界内での転職も経験している私だいすけが、実情を交えつつ解説いたしますので、ある程度リアルな情報がつかめるかと思います。
スーパーマーケットの仕事に興味を持つべき理由
「スーパーマーケットの仕事は素晴らしい。」
すでにスーパー店員としてのキャリアを捨て、フリーランスとして活動している私がそういうふうに言っても、どこか説得力に欠けるかもしれませんが、本当に素晴らしい仕事だと思っています。
この記事を読むあなたは、スーパーマーケットの仕事に興味を抱いているところなのかもしれませんね。
「自分にもつとまる仕事かもしれない」
「楽しそうかも」
「自分の住む地域へ貢献ができるかも」
あなたが心に抱くその気持ち、ぜひ大切にしてください。そう、スーパーマーケットの仕事は楽しいこともあるし、社会へ貢献できる実感も得られます。
また決して簡単な仕事とは思いませんが真剣に取り組めば、誰でもキャリアを築けます。なのでこの記事を通じて、スーパー業界に挑戦する気持ちを高めてくれたらよいなと思っています。
スーパーマーケットで働く3つのメリット

この章を通じて、スーパーマーケットで働くメリットを詳しく知っていきましょう。
1.将来性が高め
スーパーで働く大きなメリットの一つは将来性の高さにあります。食品や日用品など扱う商品には安定した需要があり、景気や社会情勢の変化に左右されづらいためです。
しかし昨今は、テクノロジーの発達によりAIに代替される業務が増えてきています。スーパーでセルフレジが導入されているのを見ると、「スーパーも人間のいらない時代が来るのかな?」なんて思うかもしれませんね。
しかし、レジの仕事は、スーパーの仕事のほんの一部でしかありません。食品加工や在庫管理、売り場作り、品出し、清掃などいたる所で人間の力がこれからも不可欠な業種です。
テクノロジーの進化や社会の変化に負けない将来性の高さがある点は、スーパーの社員になる大きなメリットです。
2.さまざまな人との出会いがある
お客さんや同僚、他部門のスタッフ、本部のスタッフ、取引先のラウンダーさんなど、スーパーマーケットで働くうえでは、たくさんの人との出会いがあります。
また、正社員は基本転勤を繰り返しながらキャリアを積んでいくため、転勤の数だけ出会いがあります。元々「人と接するのが大好き」という人なら、歓迎すべきポイントに間違いありません。
ただ、わかっています。
人との出会いが多いことを、メリットと感じるか、それともデメリットと感じるかは人それぞれですよね。「人見知り」や「コミュ障」にとっては、むしろ怖いと感じられるかもしれません。
ただ安心して欲しいのですが、私もかなり重症の人見知りです。それでもなんとかスーパー業界で一定のキャリアを築けました。スーパー業界は呼吸をするように人と話さざるを得ない環境です。人見知っている暇さえなく、コミュニケーションを取らざるを得ない環境に入ってしまえば、意外としゃべれるようになるものです。
そのため「人見知り・コミュ障を克服したい」と考える人にも、スーパー業界へのチャレンジはとてもおすすめできます。
3.キャリアアップの機会が豊富
スーパー業界には、多様なキャリアパスがあります。
企業内でキャリアを積み重ねていくための道筋
入社すると、ひとまず店内で農産・鮮魚・精肉・グロサリー(一般食品)・惣菜・サービスのうち何らかの部門に配属されます。

(私はグロサリー・医薬品担当でした)
最初に配属された部門は出発点にしか過ぎず、その後は多岐にわたるキャリア形成の道筋があります。
鮮魚担当者に配属される場合に想定できるキャリアパスを5つ挙げてみます。
- 魚の加工技術を極め、鮮魚担当者としてさまざまな店舗を渡り歩く。
- 鮮魚担当者を経て、水産物のバイヤーに転向。実績を積み鮮魚部部長に昇進。
- 鮮魚担当者を経て、水産部のスーパーバイザーに転向。その後、鮮魚部門を抜けて店長に昇進。
- 鮮魚担当者のときに、幹部に商品の売り方のうまさを買われ本部マーケティング部へ部署移動。
- 鮮魚担当者としての芽が出ず、満足な評価を受けられないまま店舗を離れ、本部配属へ。しかしマニュアル作成部門を担当すると、ピカイチの仕事ぶりで業務改善メンバーのリーダーに抜擢される。
上記はスーパーのキャリアパスほんの一例です。おもしろいのは、ある部署の仕事には適性がなくても、他の部署で才能が開花する人が結構多い点です。
「職種が無数にある、そしてチャンスも無数にある。」
スーパー業界の大きなやりがいのひとつといえるのではないでしょうか?
スーパーマーケットで働くデメリット
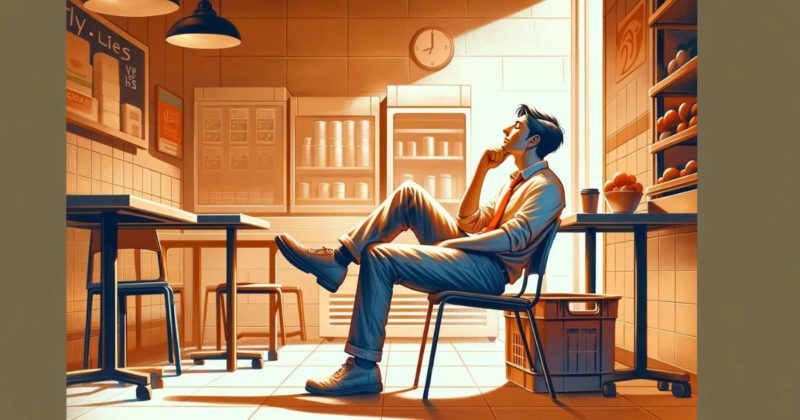
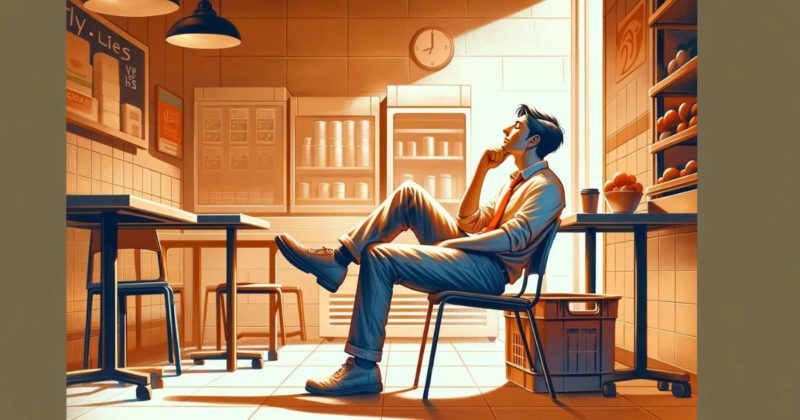
次にスーパーマーケットで働くデメリットを紹介します。
1. 不規則な勤務時間と長時間労働
スーパーは早朝から夜遅くまで営業しているのが一般的です。
パート・アルバイトは曜日や時間帯固定して働ける場合もあります。しかし社員の場合は早朝から、または午後からの勤務など勤務時間はかなり不規則です。
店舗によっては通し勤務(開店から閉店までの勤務)があったり、お盆や12月など繁忙期には残業が増えることもあり、長時間労働にもなりがちです。このように不規則な勤務時間と長時間労働がある点は、スーパーマーケットで働くうえでのデメリットといえます。
2. 肉体的な負担
スーパーでの日常業務には、肉体的な負担が伴います。
米・飲料・酒など重要品の運搬や補充作業や、レジ業務、生鮮部門の調理・加工作業における長時間同じ姿勢での立ち仕事など身体への負担が大きくなりがちです。忙しい時間帯には、休憩を取ることなくこうした業務に従事しなければならないこともあり、疲労が蓄積することもしばしばです。
いずれの部門に配属されるにせよ肉体労働が多くなる点は、スーパーで働くうえでのデメリットといえます。
3. 対人関係によるストレス
スーパーでは接客の機会が多いため、クレームが日常的に発生しがちです。
「買っていった製品が腐っていた」
「レシートを確認したら、値札と金額が違っている」
「店員の態度が気に入らない」
といった具合にほとんどのクレームは店舗側の落ち度であるため、ぐうの音も出ません。ひたすら謝罪をするのみですが、メンタルにダメージを受けます。
また最近では「カスハラ」というワードも一般的に認知されつつありますが、こちらに落ち度もないような理不尽なクレームと遭遇する可能性もゼロではありません。いずれにせよクレーム対応は一歩間違えれば、大惨事になりかねないため、かなり神経をすり減らすことになります。
また、対人関係のストレスは内部にもあります。
大きな店舗では100名以上の従業員が働くスーパーマーケットでは、人間関係の軋轢がしばしば生じるものです。



スタッフとの衝突はこれまでに結構、経験してきました。
このように、人と接する機会が豊富だからこそ、人間関係のストレスは多めな仕事といえます。
スーパーマーケットで働くのに向いている人


スーパーマーケットで働くのに向いている人の特徴を紹介します。
基本的なコミュニケーション能力のある人
スーパーマーケットでの仕事において、コミュニケーション能力は非常に重要な要素です。こう聞くと、自分には無理かなと思う方もいるかもしれませんが、別に抜群のコミュニケーション能力を持っている必要はありません。
日常的な会話ができるレベルであればOKです。
顧客とのやり取りでは、基本的な挨拶や商品の場所を尋ねられた際の案内などにおいて、親切さをもって対応できるかどうかが重要です。軽快なトークで買い物を楽しんでもらう……といった必要は全くありません。
従業員間でのコミュニケーションについても、日常会話のできるレベルなら問題ありません。
全くコミュニケーションを取らないとなると連携が悪化し、お客さんに迷惑をかけてしまうことがあるので、そうならないように報・連・相の取れる間柄を築けるくらいのコミュニケーション能力は必要です。
外から見ると話好きが集まる場所に感じられるかもしれませんが、黙々と作業する人が多いものです。
基本的なコミュニケーション能力がある人には、スーパーマーケットは働きやすい環境であるといえるかもしれません。
柔軟性のある人
スーパーマーケットでの仕事は日々変化に富んでおり、その日の顧客の流れや季節によって必要とされる業務が大きく変わります。
基本的には自分の任された部門の仕事をメインにして働きますが、「ここまでは自分の仕事、ここから先は他人の仕事」といった具合に、融通の利かない態度をとっていては歓迎されません。
一方で柔軟性が高く、さまざまな状況に適応できる人は重宝されます。例えば午前中はレジで忙しく働き、午後からは売れた部分の商品の補充に移るといったことが日常的にあります。
また野菜の鮮度を確認しながらも、店内のレジカゴを補充したり、サービスカウンターで注文対応を行なったりと、部門の垣根を超え横断的に働ける人材は強いです。
こうした姿勢で業務に取り組むことで、人より多くのスキルが短期間に身につくため、キャリアアップも早まります。
また、急なシフト変更や同僚からのフォロー依頼にも柔軟に対応し、チーム全体の働きを支える姿勢によって、職場全体の雰囲気作りにも貢献できます。
柔軟性の高さはスーパーマーケットで活躍する人材に欠かせない資質といえるのです。
細かい点に注意を払える人
細かい点に注意を払える人には、スーパーマーケットの仕事が向いています。スーパーマーケットの日常業務である、賞味期限チェックや在庫管理などの作業において、細かさが活かされるためです。
特に賞味期限の管理を怠る場合、大クレームに繋がるケースも少なくないため気が抜けません。このような環境で活躍できるのは、細かなことにも目を配り、丁寧に作業を進められる人です。
また、在庫管理においても細かい注意が必要になります。
人気商品の在庫が不足しないように注意深く監視し、必要に応じて追加発注を行うことで、顧客満足度を維持できます。一方で在庫過剰による損失を避けるため、販売データを基にした精密な在庫調整が求められます。
さらには清潔な店舗環境を保つことも、細かい注意を払う必要がある作業です。
床が常に清潔であること、棚がほこりで覆われていないこと、レジ周りが整頓されていることなど、店内のクリンリネスに気を配ることで、お客さんに快適な買い物体験を提供できます。
このように、細かな点に注意を払うことは、スーパーマーケットの業務を円滑に進め、顧客からの信頼を得るうえで非常に重要です。細部に目を配ることが得意といった長所は、スーパーマーケットの仕事において大いに活かされるでしょう。
スーパーマーケット業界への転職を目指すうえで有利になる2つのスキル


この章では、スーパーマーケット業界へキャリアチェンジ成功させるうえで、身につけておくと有利なスキルを紹介します。
接客スキル
スーパーマーケットへの転職を目指すうえでは、接客の経験・スキルを持っていると非常に有利です。
スーパーマーケットの業務は、商品を仕入れて販売するといった小売業本来の側面の他に、サービス業としての側面も色濃い仕事だからです。
お客さんと接する頻度が高いのはサービスカウンターやチェッカー(レジ業務を行う人)がメインですが、生鮮部門やグロサリー(一般食品)部門であっても、接客の機会は多いものです。
接客スキルの低い店員は、お客さんとのトラブルを起こす頻度が高くなります。すると店舗の評判が悪くなり、客数減につながってしまうわけです。
つまり、従業員一人ひとりが「スーパーマーケットチェーン全体の顔」になると考えることができます。
いくら売上や利益に貢献できたとしても、クレームの多い店員は「店頭に立たせられない人」といった烙印を押されてしまうことになりかねません。
私自身、店長として、採用に携わる場合、履歴書の職歴欄をもとに経験業種を確認しながら接客の経験をよく探っていたと思います。
よって、採用試験において接客経験があれば重点的にアピールしていくと効果的です。また接客経験が全くないという場合には、短期間でもよいので小売業や飲食業でアルバイトを経験しておくのもおすすめです。
基本的なPCスキル
スーパーマーケットへの転職を目指すうえで、「基本的なPCスキル」を身につけていることは非常に重要です。
正社員や契約社員の場合はマネジメント業務が主体となるため、パソコンの使用頻度はかなり高めだからです。たとえば商品管理や在庫確認、売上分析、スケジューリングなど、多岐にわたる業務で必要とされます。
といっても、オフィスソフト(WordとExcel)の基本的な操作ができる程度のスキルが身に付いていれば事足ります。POSシステム(販売時点情報管理)のように商品の価格を管理するシステムは、各チェーン独自のシステムを取り入れています。しかし、POSシステムの操作についても、オフィスソフトが使えていれば問題なく対応できます。
オフィスソフトの基礎スキルは書籍で独学できますが、パソコンスキルを面接時にアピールしたいということであれば資格の取得もおすすめできます。
マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)はExcelやWord、PowerPointの操作スキルに関する資格です。民間の資格のため、採用試験でどこまでのアピール力を持つかは不確実なところもありますが、オフィスソフトの基礎スキルが体系的に身につく点は見逃せません。
まとめ
この記事では、スーパーマーケットで働くメリット・デメリットや、向いている人の特徴について解説しました。スーパーマーケット業界は基本的なコミュニケーション能力を持つ人や柔軟性がある人向きの仕事ですが、専門的なスキルは求められず、基本的には誰でも就職しやすい面のある業界です。
またスーパーマーケット業界で働くメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | 雇用の機会が安定している さまざまな人と出会える 多様なキャリアパスがある |
| デメリット | 不規則な勤務時間と長時間労働 肉体的な負担が大きい 対人ストレスを受けやすい |
このようにスーパーマーケット業界で働くことには一長一短があります。メリットとデメリットの両面を考慮しつつ、キャリアチェンジを慎重に検討してみるとよいでしょう。
当メディアは、スーパーマーケット業界に挑戦するあなたを応援します。
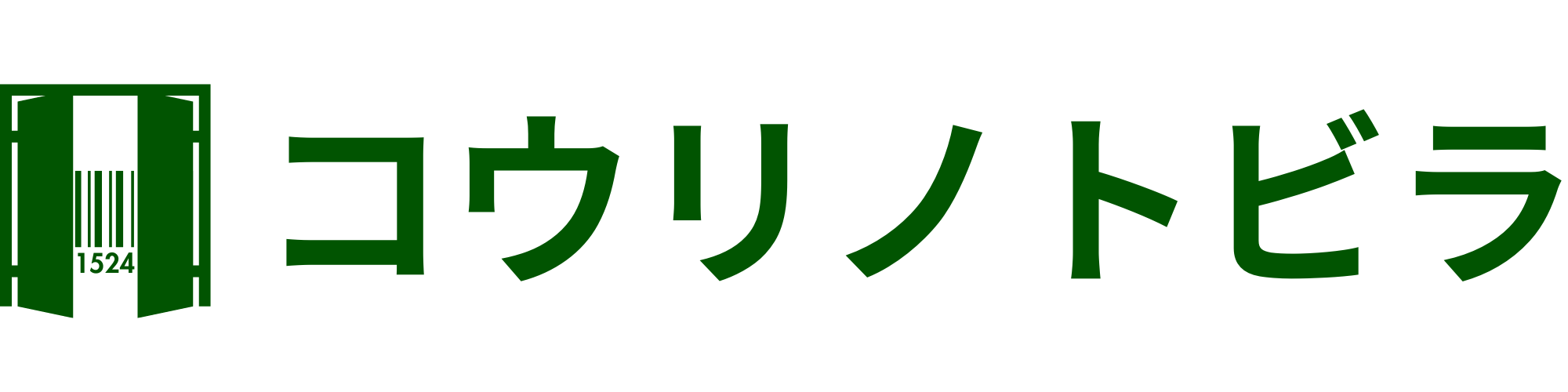
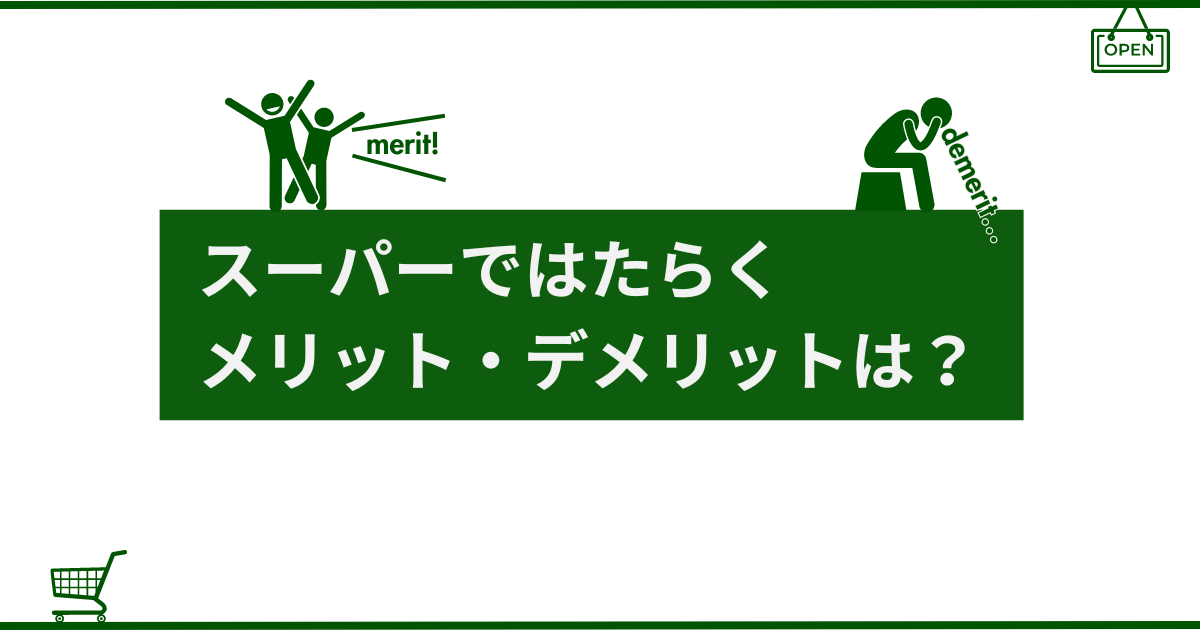
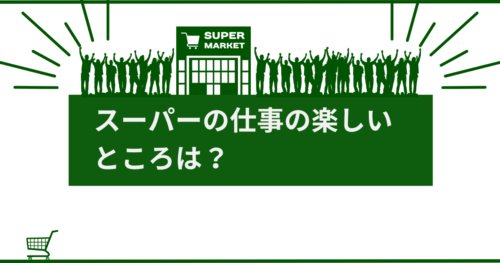

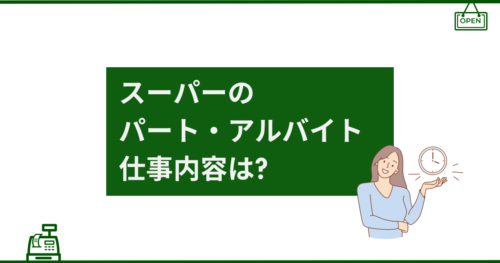

コメント