「未経験でもスーパーの正社員になれる?」
「スーパー業界に将来性はある?」
「スーパーの社員ってどんな仕事をしているのだろう」
これらの疑問をお持ちならば、ぜひ本記事をご覧ください。
この記事は、未経験でスーパーへの転職を検討している場合に、知っていただきたいことを業界経験者の目線で総合的にまとめた記事です。
スーパー業界の将来性や、正社員の業務内容、求められるスキルについて詳細に解説していますので、キャリアチェンジの際に参考にしてみてくださいね。
- スーパーへの転職にまつわる疑問を解消できる
- スーパーの正社員の仕事内容や求められるスキルがわかる
- 満足のいく環境の職場に転職できるコツがわかる
- スーパーで働く意志が湧いてくる
筆者のプロフィール
執筆者(だいすけ)のプロフィール
某ドラッグストアに3年勤務し店長経験
某スーパーマーケットチェーンに契約社員として転職
1年半で正社員へ登用
入社3年目で部門マネージャー、5年目でスーパーバイザーを経験
8年目には店長へ昇進。年収600万円達成!
現在は脱サラし、フリーランスのWebライターとして活動中(4年目)
厳しいとされる小売業界でトントン拍子に昇進を果たし、業界内での転職も経験している私が実情を交えつつ解説いたしますので、ある程度リアルな情報がつかめるかと思います。
そもそも未経験からでもスーパーの正社員になれるもの?

昨今、どの業界においても正社員として雇用されるハードルは高い状況です。
スーパー業界においても未経験者の場合、はじめから正社員として採用されるハードルはやや高めといえます。しかし、未経験向けの求人がないわけではありません。
大手求人サイト3社にて「スーパー 正社員 未経験」で検索したところ、全国の求人数は以下のとおりでした。
リクナビNEXT: 約1200件
マイナビ転職: 約150件
doda :約90件
2024年4月調査
dodaやマイナビ転職の求人数は少なめでしたが、リクナビNEXTでは比較的豊富でした。未経験でも正社員の求人に挑戦できる余地は十分にあるかと思います。
また契約社員として採用されたあと、ある程度経験を積んでから正社員へ登用されるケースもあります。

私も契約職員として入社しています。
ただし契約社員の場合ボーナスがもらえなかったり、手当がつかなかったりと正社員に比べて待遇面で劣る傾向にあります。その上、契約社員と正社員で業務内容にあまり差がないケースは意外に多いものです。
そのため、なるべく正社員を目指すことをおすすめします。
しかし、正社員として採用されるより、契約社員として採用される方がハードルが低い可能性があります。正社員の求人に応募してもなかなか採用されない場合、契約社員の求人も視野に入れる必要があるかもしれません。
スーパー業界は人材不足の傾向が強いため契約社員で採用されたとしても、仕事ぶりによっては、早期に正社員へ登用される可能性はあり得ます。



私の場合、入社から1年半後に正社員に登用されました。
※なおこの記事では、正社員・契約社員をまとめて「社員」と表現します。社員と表現されている箇所は、正社員と契約社員の両方を指しているのだなと思ってください。
スーパーの社員の将来性はある?
スーパーの社員の将来性は非常に気になるところですよね。
昨今、社会情勢の変化が激しいため、仕事の将来性について予測することは難しいものです。3年後、いや、1年後の社会の状況すら予測がつかない状況ではないでしょうか?
特にAIの発達は目覚ましく、多くの業界・職種において一部の業務がAIに置き換わりはじめています。スーパーに無人のセルフレジが設置されている様子を目の当たりにすれば、業界の将来性に疑問を抱いたとしても、なんら不思議ではありません。
こうした状況の中でもスーパーの社員の将来性は、社会全体で見ると比較的将来性が高い方ではないかと分析します。
確かにセルフレジの普及によってレジスタッフの雇用機会は奪われています。しかし、レジ業務は主にパート・アルバイトの仕事です。社員がレジに入る場面はあまり多くありません。
後ほど詳しく解説しますが、社員の主な役割はマネジメント業務です。マネジメント業務は人間ならではの複雑な意思決定が不可欠なため、AIに代替されづらい仕事といえます。セルフレジの普及が、スーパーの社員の雇用減につながる可能性は低いわけです。
また小売業界に影響を与える社会の変化として、ネットショッピングの普及が挙げられます。たとえばECサイトの利用普及が集客減の一因となり、島根県や徳島県からはデパートや百貨店が完全に姿を消しました。だからといって、百貨店と同じようにスーパーも将来的に姿を消していくとは今のところ思えません。なぜならスーパーは食料や日用品など生活必需品の供給をメインとする業界だからです。
あなたもその日に使う食材を買うなら、ネットではなくリアルの店舗が選びませんか?ネットショッピング隆盛の時代にあっても、スーパーの利用価値がなくなることはありません。
まとめるとスーパーの社員の主な業務はAIに代替されにくいとされるマネジメントです。また、食料品や日用品など生活に不可欠なものを提供しているため社会の変化に強く、比較的将来性は高いといえるのです。
スーパーはいくつかの部門の集合体
スーパーは以下のようにいくつかの部門・職種が集まって構成されています。


ここでは、入社後配属される可能性のある以下の部門の特徴を解説します。
- 食品部門
- 生鮮部門
- 惣菜部門
- サービス部門
スーパーの組織の仕組みを知ることで、どの部門で働きたいのか具体的なイメージを抱きやすくなります。
食品部門
食品部門は、加工食品や日配品、日用品を扱う部門です。スーパーマーケットで扱う商品のうち、生鮮品(野菜・肉・魚)とお惣菜以外を、すべて扱う部門と考えるとわかりやすいかもしれません。
缶詰・調味料・お菓子・飲料・米・酒・冷凍食品・アイス・トイレットペーパー・洗剤・日配品(豆腐・牛乳・パンなど期限の短い商品)
※ドラッグストアの機能を併せ持つスーパーチェーンであれば、化粧品や医薬品まで管理するケースもあります。
食品部門で扱う商品の利益は低めですが、お店全体の売上の大部分を担っています。
扱う商品群が非常に多いため在庫管理に苦労する面はありますが、生鮮部門に比べると特別なスキルが求められづらいため、未経験者でも比較的取り組みやすい部門です。
生鮮部門
生鮮部門は野菜・果物・肉・魚介類といった生鮮食品を扱う部門です。野菜・果物を扱う果物・野菜部門、魚介類を扱う鮮魚部門、肉を扱う精肉部門といった3つの部門で構成されます。
特に果物・野菜部門は生鮮部門の中でも売上の規模が大きく、店全体に与える利益への影響度も高いことから「スーパーの花形部門」と呼ばれることがあります。
鮮魚・精肉部門は、調理・加工スキルが高いほど見栄えがよく、購買意欲を刺激できる商品を作れるため「技術職の側面が強い部門」です。
食品部門と比較すると生鮮部門の売上規模は小さいものの、店の利益を左右するため、数値責任が重いところがあります。その分、数値目標を達成できたときの喜びはひとしおです。やりがいの大きい仕事を求める場合には、生鮮部門にチャレンジするとよいかもしれません。
惣菜部門
「料理をする時間がない」「片付けが面倒」といった理由から老若男女問わず、手軽に食べられる惣菜の需要は高まっています。そのためスーパーマーケットの戦略のなかで惣菜部門は重要な位置付けにある部門です。
また惣菜は店のオリジナリティを出しやすく、競合店との差別化を図りやすいところがあります。
「お弁当がボリューム満点で美味しい」
「揚げ物バイキングの種類が豊富」
「自分で作れないようなメニューが多数取り揃えられている」などなど……
これらは、お店の来店動機に直結しリピーターの増加に大いに貢献します。
そのため惣菜部門は、スーパーの集客戦略の要として、非常にやりがいの感じられる仕事です。「料理が好きな人」には、おすすめできる部門です。
サービス部門
サービス部門は、主にサービスカウンターとレジで働くスタッフで構成される部門です。商品を扱う部門ではないため、直接売上や利益に貢献するわけではありません。
ただし間接的には店の数字に影響します。サービスの質が高まるほど顧客ロイヤリティ(店舗への信頼・愛着の大きさ)も向上し、客数アップにつながるからです。
サービス部門ではレジ業務のほかに包装や特別注文への対応、配送品の受付、返品・交換など、お客さんの買い物をサポートします。時には、クレームの窓口になる事もあるため、的確に担当部署へ取次ぐ判断力も必要です。そのためサービス部門は、高い接客スキルや柔軟性などを求められる部門といえます。
接客スキルを極めたい場合には、サービス部門がおすすめです。
スーパーの正社員の業務
この章では、スーパーの正社員の業務にはどのようなものがあるかを紹介します。具体的には以下の7種類があります。


マネジメント
マネジメントとは「何かを管理する仕事」のことを指します。
スーパーの社員にとって「マネジメント」は非常に、非常に重要な業務の一つです(大切なことなので”非常に”を2回言います)。
社員は有形無形問わずに、多岐にわたる対象を管理することになります。
有形の管理対象:商品・お金・備品・人
無形の管理対象:売上・利益・コスト
入社後すぐに取り組むマネジメント業務としては、在庫を整理整頓して発注時の過不足を防いだり、パート・アルバイトが休憩に入る時間をコントロールして業務が円滑に回るようにしたりといったことが挙げられます。
キャリアアップするほどにマネジメントする対象は増えます。そのため、スーパーの社員としてキャリアを築くためには、高度なマネジメントスキルが求められるわけです。
パート・アルバイトのマネジメントできない社員は、店の運営を崩壊させるかもしれません。(余談なので読みたい人だけ開いてくださいね)
スーパーの社員にとって永遠の課題になるのが「パート・アルバイトの勤務状況をマネジメントすること」です。いかにパート・アルバイトに効率的に働いてもらう環境を作っていくかは非常に重要です。
具体的に、以下の点に気をつけていました
- 残業が生じないように、無理ない作業量の割り振りを行う
- 倉庫を整理して、パートさんが発注がしやすいように整える
- 朝礼やミーティングの進行表を作成して連絡が漏れないようにする
- 売り場計画を早い段階で共有して、入荷当日に作業しやすいように心がける などなど…
たとえば連絡漏れによって「あの人は聞いているのに私は聞いていない」といったことがパートの間に生じると、すぐさまモチベーションダウンにつながり生産性が悪影響を及ぼします。
一方でときにパート・アルバイトに厳しく指導しなければならない時があります。そんな中、自身がマネジメントを疎かにしてだらしない姿を見せていると、パート・アルバイトから反発を受けることは必至です。
パートさんにそっぽを向かれては、店舗運営は全く立ち行かなくなります。



パートさんとの関わりは本当に気をつけた方が良いです。
スーパーの社員はいかにマネジメント力を発揮できるかで、評価の大部分が決まってしまうといっても過言ではありません。
品出し・前出し(前陳)
品出しとは入荷した商品を適切な場所に並べたり、売り切れた商品を補充したりする業務です。ただ商品を棚に置けばよいのではなく、顧客が見つけやすいようにパッケージの表面を前に向けて並べます。
一方の前出し(前陳)とは、売れてしまって少なくなっている商品を奥から引っ張り出して、売り場のボリューム感を維持する業務です。前出しを怠ると売り場が穴だらけのようになってボリュームがなく見えたり、まだ棚の奥には在庫が残っているのに売り切れてしまったように見えたりします。



グロサリー部門においては、品出しと前だしはセットで行うように入社直後に叩き込まれます。
競合調査
競合調査とは、近隣の店舗に足を運び、価格や売場レイアウト、品揃え、販促活動、顧客サービスの質などを調査することを指します。競合調査を通じて自店舗の強み・弱みを客観的に把握し、次の戦略を立案できるようになるのです。


競合調査に行くべき頻度は、部門によって異なります。
食品部門なら週に数回で良いですが、日々売り場が切り替わる生鮮部門ならば毎日調査にいくことが望ましいでしょう。お盆や年末年始など年間でも重要な時期には、午前中と夕方の1日2回視察に行く場合もあります。
ただし入社直後は一人で競合店を訪れても、調査すべきポイントがよくわからないかと思います。そのため上司に同行して調査を行い、どんなところを見ているか学ぶのがベストです。
在庫管理
在庫管理とは、必要な量だけ商品をストックし、在庫の過不足を避けるための業務です。
倉庫の整理整頓は在庫管理の業務の中でも特に重要です。整理整頓された倉庫では、発注の重複や必要な商品の発注漏れの防止が容易になり、適正な在庫量の維持におおきく貢献します。
また生鮮食品のような品質が重要な部門では、適切な在庫量の維持が商品の鮮度を保ち顧客満足度を向上させるための鍵です。



野菜や魚が入荷しては即売れするので、
常に新鮮な状態が保たれている状態です。
また在庫管理にはデータ分析も欠かせません。
セール商品など特別な価格で仕入れるアイテムは、数週間前から計画的に発注する必要があります。直近の販売量と前年同時期の販売データを基に将来の売上予測を立て、適切な在庫数を確保します。これは売り逃しを防ぐために重要です。
棚卸し
棚卸しとは端的に言うと、利益を確定させる業務です。
スーパーでは、レジを経由して売上と利益が大元のシステムに日々計上される仕組みになっています。しかし。システムに計上されている金額が正確な数値とは限りません。実際にはレジの打ち間違いや商品の誤納、万引きによって、気付かぬうちに損失が発生しているかもしれないからです。
そこで商品の数量を実際に数えて、店にある在庫高を明らかにすることで本当の利益と損失額を算出します。


棚卸しの頻度は、部門によって異なる場合があります。
生鮮部門や惣菜部門においては毎週棚卸しを行い、週ごとに正確な利益を確定しますが、食品部門は、取扱品目が膨大なため、毎週の棚卸しは物理的にムリです。そこで、食品部門については年に1〜2回ほど、外部業者に依頼して、商品を数えてもらうことになります。
在庫管理が不十分だと、大きな損失が後から発覚して担当者は憂き目を見ることもあります。そのため棚卸しの結果は、「社員のマネジメント力に対する通信簿」といえるかもしれません。
売り場作り
スーパーの社員にとって、売り場作りは重要な業務です。本部のバイヤーが用意した企画や季節感や考慮しつつ、どの商品を打ち出すかを決め売場を構築していきます。
またお客さんは献立を決めずに来店する場合が多いため、メニュー提案のできる売り場作りが重要です。そこで社員は関連陳列を意識します。
ある料理に関連する食材を一つの売り場にまとめる手法。たとえば、白菜やネギなどの野菜と一緒に鍋スープを配置したり、焼肉用の牛肉の近くに焼肉のタレを陳列したりする。
関連陳列を通じてお客さんは「今晩は鍋にしようかしら」といった具合に、献立を決めることができ、結果として商品の販売に繋がります。
このように意図して、購買意欲が刺激されるような売り場をコーディネイトしていくことは社員の仕事です。
接客
スーパーでは、接客の機会が豊富です。
接客業務のウエイトが大きいのはサービス部門に属する社員ですが、他部門の社員も商品の案内をしたり、商品の解説をしたりと顧客と接する機会は頻繁にあります。
またクレーム発生時の対応はパートさんやアルバイトに任せられるものではないので、社員が全面的に対応することになります。
業界未経験の場合、クレーム対応については、とりわけ不安を感じるところではないでしょうか?
もちろん入社直後は社員といえども、クレームへの対処の方法がわからないのが当然です。直属の上司や、店長にクレームを引き継いでしまえば問題はありません。落ち着いてクレームの内容や経緯を引き継げるかどうかが大切です。上司や先輩が対応する姿を見ながら、クレームへの対処法を学んでいくことになります。



必要以上に構えなくても大丈夫です!
スーパー店員のやりがい


労働へ向かうモチベーションを保ち、長く働き続けるためには仕事を通じて「やりがい」を感じることが重要です。この章では、スーパーに転職することで感じられるやりがいには何があるのかを解説します。
地域に貢献できる
スーパーで働くことで、地域貢献ができます。
スーパーは人間が生きていくうえで欠かせない食料品を供給している場です。住民にとってのライフラインになるため、地域への貢献度は非常に高いところがあります。
また地元の生産者から食材を仕入れて、経済活性化に貢献できたり、イベントを企画・開催して、お客さんへエンターテインメントを提供できたりと、貢献できる場面は多様です。
営業数値を通して仕事の成果を実感できる
スーパーでは売上・利益・客数・販売点数など、数値を通じて成果が常に可視化されます。自身の努力や工夫によって、こうした数字が好転していく体験を味わえば、仕事のおもしろさは倍増していきます。
たとえばあなたが「秋の味覚フェア」を企画し、パート・アルバイトと商品選定やディスプレイのアイデアを出し合い、チームで売り場を作ったとします。企画が成功して大きな売上を作れれば、チームで喜びを分かち合えます。



個人的には、チームで喜びを分かち合うときが
最高の気分でしたね!
成功体験が積み重なるごとにキャリアアップの可能性も高まっていくのも特色の一つです。
とはいえ経験の浅いうちは、日常業務をこなすので精一杯だと思います。1日も早く日々の業務に慣れ「数値」に対して意識を向けられるようになると、仕事のやりがいは高まっていきます。
キャリアアップの機会が豊富
スーパー業界には、多様なキャリアパスがあります。
企業内でキャリアを積み重ねていくための道筋
入社すると、ひとまず店内で農産・鮮魚・精肉・食品・惣菜・サービスのうち何らかの部門に配属されます。



(私は食品・日用品・医薬品担当でした)
最初に配属された部門は出発点にしか過ぎず、その後は多岐にわたるキャリア形成の道筋があります。
鮮魚担当者に配属される場合に想定できるキャリアパスを5つ挙げてみます。
- 魚の加工技術を極め、鮮魚担当者としてさまざまな店舗を渡り歩く。
- 鮮魚担当者を経て、水産物のバイヤーに転向。実績を積み鮮魚部部長に昇進。
- 鮮魚担当者を経て、水産部のスーパーバイザーに転向。その後、鮮魚部門を抜けて店長に昇進。
- 鮮魚担当者のときに、幹部に商品の売り方のうまさを買われ本部マーケティング部へ部署移動。
- 鮮魚担当者としての芽が出ず、満足な評価を受けられないまま店舗を離れ、本部配属へ。しかしマニュアル作成部門を担当すると、ピカイチの仕事ぶりで業務改善メンバーのリーダーに抜擢される。
上記はスーパーのキャリアパスほんの一例です。おもしろいのは、ある部署の仕事には適性がなくても、他の部署で才能が開花する人が結構多い点です。
「職種が無数にある、そしてチャンスも無数にある。」
スーパー業界の大きなやりがいのひとつといえるのではないでしょうか?
スーパーの社員に求められる能力


この章では、スーパーの社員に求められる能力を紹介します。
体力
スーパーマーケットでの日常業務には肉体的な負担が伴うため、体力勝負です。
メインで扱う商材の中には米や飲料、酒など重量品が含まれ、こうした商品の運搬や補充など物理的な作業は、体への負担が大きくなりがちです。また生鮮部門の調理業務やレジ業務における長時間同じ姿勢での立ち仕事も体へ負担を与えます。
忙しい時間帯には、休憩を取ることなく連続して働かなければならない状況もあり、肉体疲労を蓄積させる要因となることがしばしばです。
そのためスーパーの社員には、ある程度の体力が求められます。
マネジメントスキル
人・物・お金など経営資源を管理するのが社員の主な役割のため、マネジメントスキルは重要な能力の一つです。
基本的にスーパーの社員は、遂行すべき作業に必要な人員を配置して、売上目標や利益目標などの課題を効率的にクリアできるようにコーディネイトする役割を担います。人員が不足している場合には、品出しや清掃など単純作業を自ら行う場合もありますが、みだりに作業に加わるのは本来の姿ではありません。



上司から「社員は作業員になるな」と口すっぱく言われました。
よって作業のスキルばかり磨いていても、マネジメントができなければ社員として評価を受けることはできないわけです。
経営資源を効率的に活用しながら、与えられた課題をクリアしていくための「マネジメント能力」は、スーパーの社員に最も求められるスキルの一つといえるかもしれません。
接客スキル
商品を仕入れて販売するといった小売業本来の側面の他に、サービス業としての側面が色濃い仕事のため、スーパーで働くには接客スキルが重要です。
お客さんと接する頻度が大きいのはサービスカウンターやレジに立つ人がメインになることは間違いありませんが、生鮮部門や食品部門であっても、接客の機会は多いものです。
つまり「従業員一人ひとりがスーパーマーケットチェーン全体の顔」になるわけです。
接客スキルの低い店員は、お客さんとのトラブルを起こす頻度が高い傾向にあります。いくら売上や利益に貢献できたとしても、クレームの多い店員は「店舗に立たせられない人材」といった烙印を押されてしまうことになりかねません。
臨機応変な対応力
スーパーマーケットでの仕事は日々変化に富んでおり、その日の顧客の流れや季節によって必要とされる業務が大きく変わります。
基本的には自分の任された部門の仕事をメインにして働きますが、「ここまでは自分の仕事、ここから先は他人の仕事」といった具合に、融通の利かない態度をとっていては歓迎されません。
一方で柔軟性が高く、さまざまな状況に適応できる人は重宝されます。たとえば午前中はレジで忙しく働き、午後からは売れた部分の商品の補充に移るといったことが日常的にあります。
また野菜の鮮度を確認しながらも、店内のレジカゴを補充したり、サービスカウンターで注文対応を行なったりと、部門の垣根を超え横断的に働ける人材は強いです。
こうした姿勢で業務に取り組むことで、人より多くのスキルが短期間に身につくため、キャリアアップも早まります。
また、急なシフト変更や同僚からのフォロー依頼にも柔軟に対応し、チーム全体の働きを支える姿勢によって、職場全体の雰囲気作りにも貢献できます。
柔軟性の高さはスーパーマーケットで活躍する人材に欠かせない資質といえるのです。
食への関心
スーパーの社員として働くうえで「食への関心」を持っているかどうかは、個人的に非常に重要だと思っています。
といっても入社時点では「料理がわりと好き」や「新商品をつい買ってしまう」など、人並みの関心で十分です。
食に関心が高ければ高いほど、食品を買い求めにくるお客さん気持ちを理解し、購買意欲を刺激する売場を構築できます。逆に食に興味が薄いと、顧客のニーズを捉えるのが難しくなります。
また食への関心の有無は、キャリア形成に影響を及ぼしかねません。
たとえば店舗のトップである「店長」は、店全体のコーディネイトが主な役割です。スーパーの全部門に横串を入れ、総合的な営業戦略を組み立てなければならなくなります。この段階になると、食に関する幅広い知識がなければ、効果的な戦略を打ち出すことができません。
入社直後は商品知識が乏しくても業務をこなせますが、キャリアを重ねるほど深い食の知識が求められるものです。
一方、食に関心がある人ならば、楽しみながら食の知識をさらに深めていけるためキャリアアップにも対応できます。ところが食に関心のない人が無理に食の知識を学ぼうとしても苦痛になりかねないのです。
このように「食に対する関心」は、スーパー業界での活躍するための鍵です。
より良い環境で働くために意識するとよいこと
一口にスーパー業界へ転職するといっても、企業によって労働環境はさまざまです。この章では、より良い環境で働くために意識すべきことを紹介します。
大手のチェーンへの就職がおすすめ
大手のスーパーチェーンには景気の動向に左右されづらい安定した経営基盤があります。福利厚生の充実度も高く、安心して働ける企業が多い点も見逃せません。
小規模なスーパーの場合は、経営の安定性に不安が残ります。
私が所属するスーパーの近隣には、地元密着型の小規模なスーパーがありました。
近隣の住民に愛されていて賑わっている印象でしたが、ある日突然倒産してしまったのです。しかもそこからさらに1年ほど前に、私の所属するスーパーから倒産したスーパーへとある若手社員が転職していったばかりでした。きっと彼も、転職先の会社がすぐに倒産してしまうとは思いもよらなかったでしょう。
このように小規模なスーパーに転職することは、リスキーな面があります。
転職エージェントを利用する
満足のいく職場環境を見つける過程で、転職エージェントの利用は非常に有効な手段の一つです。転職エージェントとは、職を探す人と雇用したい企業を仲介させるサービスを指します。
転職エージェントは希望する労働条件や経験、適正に基づき、転職活動のアドバイスと求人情報を提供してくれます。
また転職エージェントのサービスは助言や求人紹介に留まりません。
履歴書や職務経歴書の作成支援、面接対策のアドバイス、給与や勤務条件の交渉などのサポートも含まれます。自力での転職活動に比べ効率が大きく向上し、満足できる環境へのキャリアチェンジを実現しやすくなるわけです。
スーパー業界への転職を目指す際にも、転職エージェントの活用がおすすめです。というより、利用しない理由が見つかりません。
まとめ
この記事では、スーパーの正社員になる方法や業界の将来性、およびスーパーで働くことのやりがいについて解説しました。
スーパー業界においては、未経験者向けに正社員の求人があるため挑戦の余地はあります。
ただしスーパー業界には向き不向きが存在するため、本記事を参考に、仕事内容や求められるスキルを確認しなつつ、慎重にキャリアチェンジを検討してみてください。もしスーパー業界に進むと決めたなら、自身に適した求人に辿り着きやすい転職エージェントの活用はおすすめです。
当メディアは新たなキャリアの第一歩を踏み出すあなたを応援します。
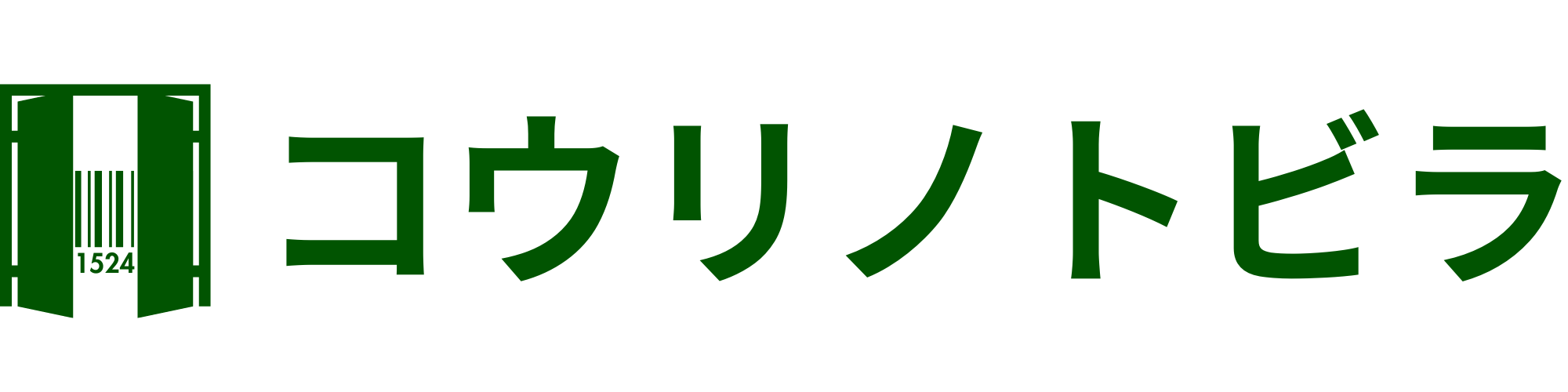
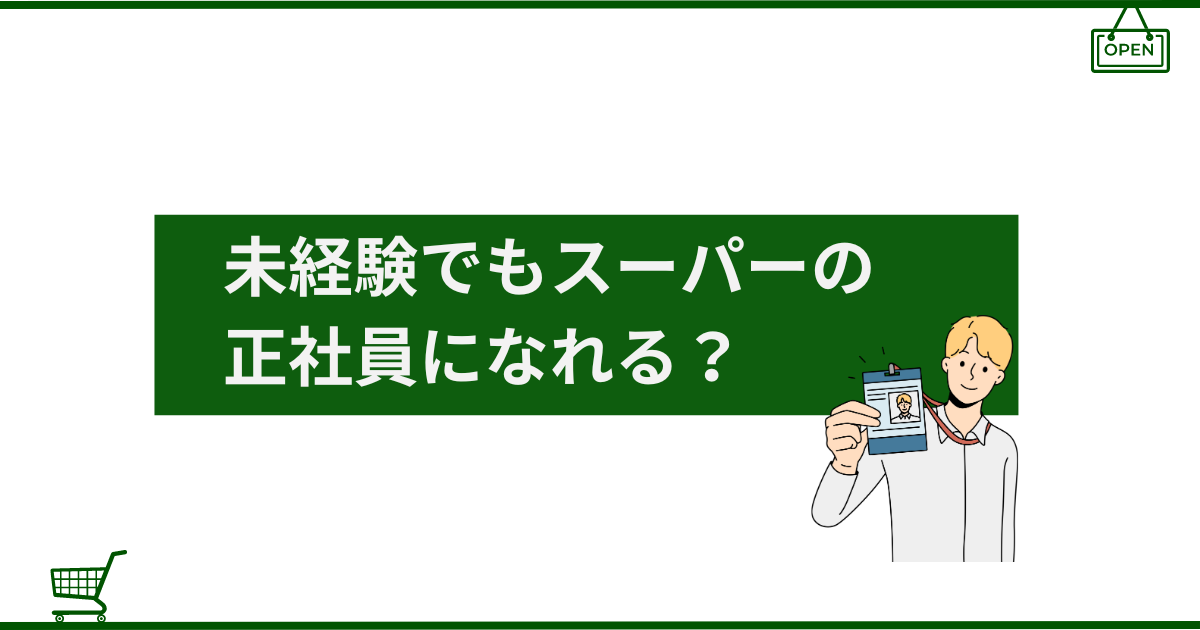
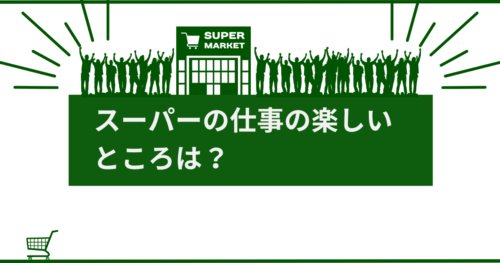

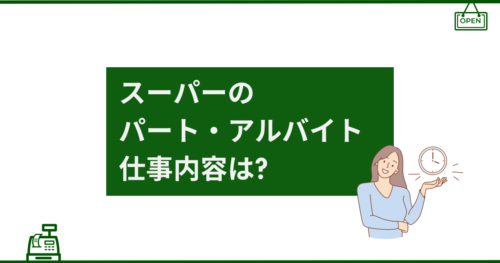
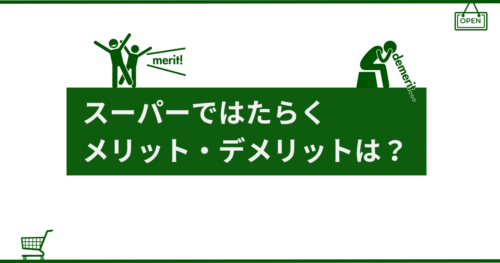
コメント